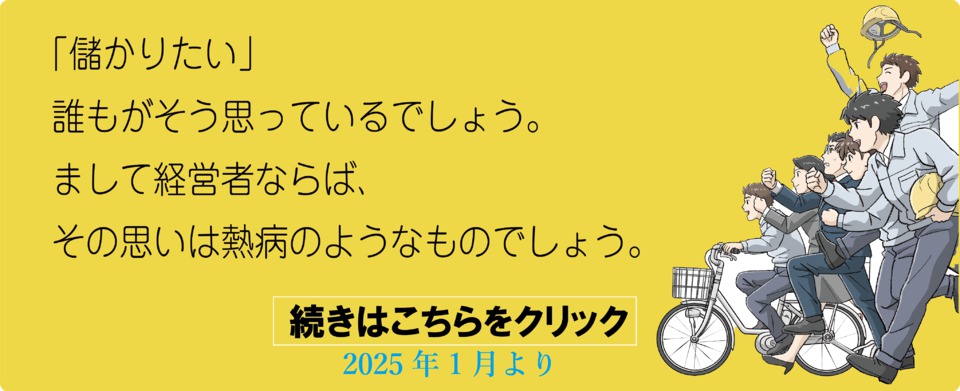「儲かる仕組み」の理解(その8):その総括
2025.08.26
「儲かる仕組み」の理解(その8):その総括
ここまで解説した「儲かる仕組み」の7つのポイントを以下に総括します。
【その1:儲けの方程式】

儲かる仕組みは、以下の2つの要素を組み合わせて作ります。
A:「一か八か」に掛け、一攫千金の儲けを狙う
B:持続的な儲けに繋がる「全員参加の仕掛け」を作る
「強い経営」とは、Bをメインにしながら『いざ』という時に、すぐに使えるようにAを手法化しておく経営です。
建設会社の儲けは「売上額」と「原価」、「経費」の「三体問題」となります。
三体問題は数学的には解けない問題です。
ゆえに、三体のどれかを“仮に”固定する計算を繰り返し、確率の重ね合わせで解を求めていく必要があります。
【その2:等価交換が商売の大原則】
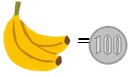
等価交換は、価値が同じもの同士を交換するという「物々交換」
がその原点です。
商売の売り手側は、そのうえに、付加価値という名の別の価値を
加えて売るわけです。
建設工事の難しさは、工事が終わるまで、その工事の儲け(損失)がPL(損益計算書)
には現れず、BS(貸借対照表)にそれに繋がる要素が現れるに過ぎない点です。
そのBS上でも、工事完成高(つまり売上)は工事完成の時まで、一切出てこない。
それが厄介なのです。
【その3:利益の相反構造】

物品販売などの商売では、等価交換の原則がシンプルに働きます。
しかし、実際は結構難しいですね。
どうしてでしょうか?
誰もが「自分に利がある取引」を狙うからです。
その結果、商売の儲けは「等価交換」と「利益の相反」の駆け引きの中に紛れてしまい、外からだけでなく、内側からも見えにくくなります。
売り手側は、こうした対立構造を顕在化させずに、買い手に対しては「妥当な価格だ」、できれば「お得だ」と思わせる工夫が必要になります。
宣伝広告は、そのための営業手段なのですが、SNSの登場で、その方法は様変わりし始
めています。 「さあ、どうする?」
【その4:「時は金なり」=おカネは回転して増えていく】

経済は、生産と購買の2大要素で成り立っています。
そして、この両輪を回す原動力が「おカネ」で、
「情報」がその潤滑油となります。
ところが、もともとは両輪をスムースに回すための
潤滑油に過ぎなかった「情報」ですが、ビジネスの回転がどんどん速くなり、また複雑に
なるにつれ、「情報」は両輪である2大要素以上に重要な存在になってきています。
このように、経済要素の主客逆転が起きているのが現代です。
この「情報」が、高級かつ良質な潤滑油になるには、「正確」さと同時に「タイムリー」
であることが必要です。
情報化時代の現代では、「生産」以上に「情報」の重要性が高まっているのです。
【その5:賃上げと値上げの好循環】

近年の政府の口癖になっている「賃上げと値上げの好循環」
ですが、言葉だけで「中身が空っぽ」です。
ゆえに、賃上げ以上に物価が上がり、国民意識はデフレ・
マインドから抜けだせないままになっています。
景気浮揚には、この沈滞したデフレ・マインドに効果的な呼び水を掛ける必要があります。
即効性があるのは「政府による大きな直接投資」です。
公共工事は、その代表的な投資なのですが、財務省は「プライマリーバランスが大事」と
渋い顔で反対し、増税路線を堅持する姿勢を変えようとしません。
首相は、こうした路線を変える権限を持っているにもかかわらず、今の首相はまったくの
無為無策。
民間企業としては、こうした政府の無策を嘆いていても仕方ないので、自社独自の好循環を
作り出す知恵を絞り、努力を続けるしかありません。
【その6:おカネは時間で考える】

「儲かる仕組み」を創ることは「カネと時間」の2つを関数とする自社独自の方程式を
作る行為です。
IT産業や「モノ売り産業」と違い、建設産業はリアルな「ものづくり産業」の一つで、しかも、一品ものを作って提供するという、売上確定および資金回収の時間がかかるという弱点の多い商売です。
それなのに、人件費はもちろん資材の購入など、どうしても先にお金が出ていく要素の多い商売です。
「おカネを時間で考える」とは、こうした時間差に備えるための資金確保を計算し、コントロールすることを意味します。
具体的には「固定費の何か月分の資金を確保しておくべきか」を決めることです。
その結果で、手持ち資金が足りていればOK。
もし不足しているならば、借入を増やしでても、その水準までの資金を確保すべきです。
これは、ちょっと計算すればすぐに分かる指標ですが、重視している企業はあっても、
きちんとした計算式や基本数字を管理できている企業は、まだまだ少数です。
【その7:「儲けさせる」ことが「儲け」となる】

どんな企業でも、自社の利益を優先したいのは当たり前です。
しかし、その気持ちをコントロールできてこその上級経営です。
それには、まず自らの意識を中庸(何も決定しない状態)状態において考えることが
大事です。
難しいですか?
それでは、以下のことを考えてください。
お客様や協力会社など、自社とビジネスで繋がっている「他社を儲けさせることで自社が儲かる」という構図を考え、少しずつ作っていきませんか。
こうした構図が作れて、実践できたら、間違いなく“儲かる”会社になります。
しかし、そのことに気付き、『よっしゃ、やるぞ!』と決意しても、そう簡単な話では
ありませんね。
まずは、小さな“できること”から始め、少しずつ対象範囲を広げていくことです。
こうして「スパイラル(螺旋)階段」を上がるように、回りながら、
少しずつ上に上がっていくことです。
その仕組みを“PDCAサイクル”で回しながら、この螺旋階段を上が
っていけば、必ず儲かる会社になります。
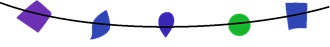
第1部「儲かる仕組み」の理解は、ここまでです。
この第1部を何度かお読みいただき、この仕組みを理解された頃に、次の第2章のUPを行う予定です。
この第2章は、「儲ける仕掛け」作りの実践です。
期待しながら、第1章を再度お読みください。