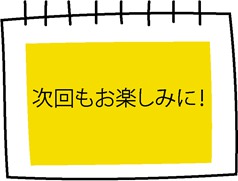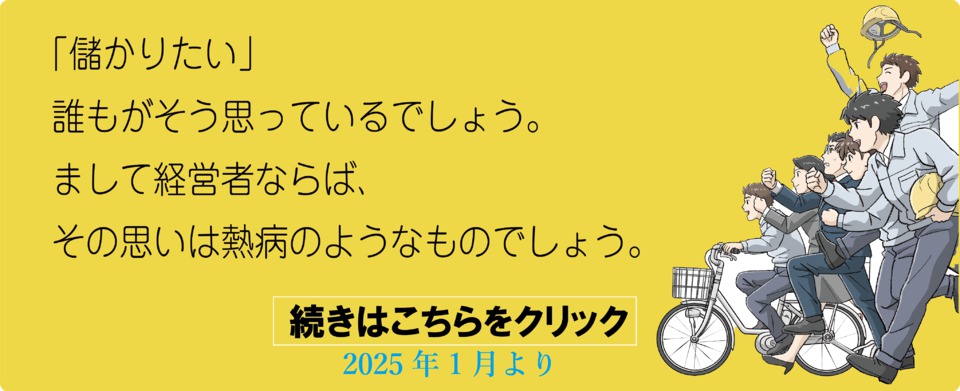「儲かる仕組み」の理解(その6):おカネは時間で考える
2025.05.07
「儲かる仕組み」の理解(その6):おカネは時間で考える


前回(その5)、自社の企業活動の全てを「カネと時間で考えていく“クセ”を付けてください」と書きました。
この話をもう少し進めます。
 当たり前のことですが、どんな企業活動にも時間が掛かります。
当たり前のことですが、どんな企業活動にも時間が掛かります。また、当然、おカネが掛かります。
つまり「儲かる仕組み」を創るとは、この2つ(カネと時間)
を関数とする方程式を創ることです。
方程式と聞くと「頭が痛くなる」と言われるかもしれませんね。
まあ、小学校からの算数・数学教育の効果(?)で数字が苦手
という方は多いようですね。
でも、心配しないでください。
本ブログは、読んでくださる方々に対し、学校のように「何かを教える」ことが目的ではありません。
儲ける仕組みを理解し、儲かる仕組みを作り、そして儲けてもらおうという目的のブログです。
その目的を理解していただいて、先へ進もうと思います。
時間を掛けずに大きなおカネを得たいのは、多くの人の願望でしょう。
そのような方程式を創って運用することが大儲けの道です。
そこに「そんな方程式なんか要らずに、その夢、実現しますよ」と甘くささやき、人々を引き込む商売がカジノ産業(あらゆる賭け事)です。

この甘い“ささやき”は強い力を持ち、実際に多くの人が引き込まれています。
しかし、国民の大半がカジノ産業に引き込まれ、短絡的なおカネ稼ぎしか行わなかったら、その国は潰れます。
それはそうですね。
生活に必要なモノ作りやサービスを行う人がいなくなったら、国家は成り立ちませんから。
・・・
しかし、国民の大半がカジノ産業に引き込まれ、短絡的なおカネ稼ぎしか行わなかったら、その国は潰れます。
それはそうですね。
生活に必要なモノ作りやサービスを行う人がいなくなったら、国家は成り立ちませんから。
・・・

こう書くと、「モナコ王国はカジノの利益で賄っていて、所得税はゼロだよ」と仰る方、けっこうおられるのではないでしょうか。
でも、本当にそうなんでしょうか。
でも、本当にそうなんでしょうか。
たしかにモナコ王国、かっては国家収入の95%がカジノ収入でしたが、今は5%程度しかありません。
それでも、個人の所得税はゼロで、世界中から大金持ちたちが集まって来ることは、昔と変わっていません。
現在のモナコ王国の国家収入の約50%は付加価値税(消費税)であり、残りは法人税、相続税、不動産収入などです。
つまり、観光やサービス業などの高い利益で、法人税は結構豊富に入るようです。
その結果、国家財政は豊かで、国家は歳出額の1年分ぐらいを基金で保有して、その基金がさらなる利益を得るという好循環の経済を作っています。
“羨ましい”国であることには変わりませんね。
さて、なんでモナコ王国のことを書いたかと言うと、我々中小企業の手本になると思ったからです。
どうでしょうか。米国や中国、日本などの経済大国とは全く違うモナコ王国の経済運営は、中小企業の生きる道の参考になると思いませんか。
前述したように、モナコ王国の現在の主産業は、観光とサービス産業、金融業です。
つまり、金融業は別にして、外から大勢の人が訪れることが絶対条件です。
ネット全盛の時代ですが、ネットでは味わえないリアルさが人を引き寄せる最大の要素となっています。
つまり、金融業は別にして、外から大勢の人が訪れることが絶対条件です。
ネット全盛の時代ですが、ネットでは味わえないリアルさが人を引き寄せる最大の要素となっています。


さて、ここで建設業の話に戻ります。
私たちの事業の場である建設業はリアルな「ものづくり産業」です。
 それなのに、昨今はICTとかBIMとかの言葉に惑わされて、どんどんとリアルさを失っているように思うのです。
それなのに、昨今はICTとかBIMとかの言葉に惑わされて、どんどんとリアルさを失っているように思うのです。
もとよりシステム化を否定するものではありませんが、システムと人間とが主客逆転するような風潮が広がっていくことに危うさを感じるのです。
私たちの事業の場である建設業はリアルな「ものづくり産業」です。
 それなのに、昨今はICTとかBIMとかの言葉に惑わされて、どんどんとリアルさを失っているように思うのです。
それなのに、昨今はICTとかBIMとかの言葉に惑わされて、どんどんとリアルさを失っているように思うのです。もとよりシステム化を否定するものではありませんが、システムと人間とが主客逆転するような風潮が広がっていくことに危うさを感じるのです。
製造業は、すでにロボット生産が主体になり、半導体製造などは人間が入り込む余地はゼロになって
います。ゆえに、遠い将来を考えれば、建設業のロボット化も進むでしょう。

しかし、建設業は製造業と違い、物づくりの場所の多くが工場ではなく、屋外、そ
れも場所が一定化しないという制約があります。
その制約から、施工方法の標準化は限定的になり、作業場所の条件や作業する人の力量に左右されるようになっています。
大半がロボット施工になる日は、まだまだ遠い話です。
大半がロボット施工になる日は、まだまだ遠い話です。
さらに、この制約によりコストのばらつきが大きくなり、利益確保の不安定さに繋がっています。
また、受注生産の常で、実際におカネを得るまでの時間が長くなり勝ちです。
こうした収支の不安定さに無頓着な会社が行き詰るのは当然で、多くの会社は経営計画の中に資金管理計画を入れています。
しかし、計画したからといっておカネがその通りに出入りすることは少なく、常に狂います。
だから、そうした計画の狂いに備えて一定額の資金確保をしておくことが必須となっています。
では、その金額はどのくらいが適正なのでしょうか。
ネットの世界では、税理士やコンサルタントの方が、固定費の3か月とか6カ月の資金確保とか言っています。
この金額は、入金がゼロになっても企業が耐えられる月数をベースにしています。
もちろん、業種や重層下請け構造における自社の立ち位置などによってこの値は変わります。
大事なことは、自社の条件に合わせて、自社なりの計算基準を確立し、その基準のメンテを続けることです。
さらに、計画の狂いに備えて、二次、三次を含めた資金調達手段のメンテも怠らないことです。
ここまで述べてきたことの計算が、冒頭で述べた「おカネと時間」の関数計算式なのです。
3か月とか6カ月とかの月数は目標となる数字ですが、達成するための計算式を確立して算出する客観的な結果であることが大事です。
「そんな計算など面倒」と言われる方は、では、大きな目標を作ってください。
例えば、12ヶ月とか18ヶ月ぐらいの大きな目標です。
つまり、1年か1年半ぐらいの間、入金がゼロでも生きていける目標です。
弊社は18か月を目標に掲げていますが、近づいたと思ったら、また離れて・・と、なかなか達成できていません。
でも、近づく努力は、この先も続けていきます。
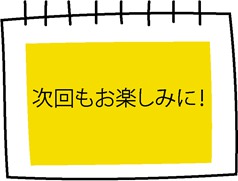
また、受注生産の常で、実際におカネを得るまでの時間が長くなり勝ちです。
こうした収支の不安定さに無頓着な会社が行き詰るのは当然で、多くの会社は経営計画の中に資金管理計画を入れています。
しかし、計画したからといっておカネがその通りに出入りすることは少なく、常に狂います。
だから、そうした計画の狂いに備えて一定額の資金確保をしておくことが必須となっています。
では、その金額はどのくらいが適正なのでしょうか。
ネットの世界では、税理士やコンサルタントの方が、固定費の3か月とか6カ月の資金確保とか言っています。
この金額は、入金がゼロになっても企業が耐えられる月数をベースにしています。
もちろん、業種や重層下請け構造における自社の立ち位置などによってこの値は変わります。
大事なことは、自社の条件に合わせて、自社なりの計算基準を確立し、その基準のメンテを続けることです。
さらに、計画の狂いに備えて、二次、三次を含めた資金調達手段のメンテも怠らないことです。
ここまで述べてきたことの計算が、冒頭で述べた「おカネと時間」の関数計算式なのです。

3か月とか6カ月とかの月数は目標となる数字ですが、達成するための計算式を確立して算出する客観的な結果であることが大事です。
「そんな計算など面倒」と言われる方は、では、大きな目標を作ってください。
例えば、12ヶ月とか18ヶ月ぐらいの大きな目標です。
つまり、1年か1年半ぐらいの間、入金がゼロでも生きていける目標です。
弊社は18か月を目標に掲げていますが、近づいたと思ったら、また離れて・・と、なかなか達成できていません。
でも、近づく努力は、この先も続けていきます。