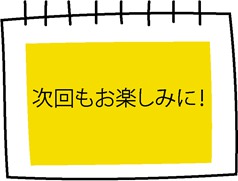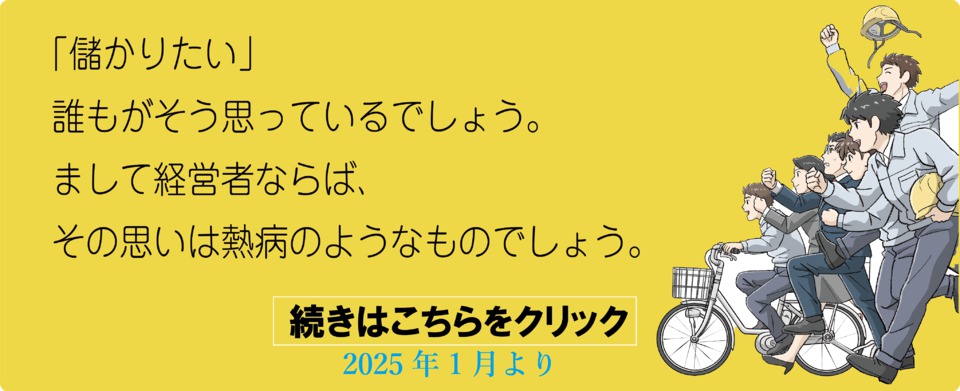「儲かる仕組み」の理解(その4):「時は金なり」=おカネは回転して増えていく
2025.03.06
「儲かる仕組み」の理解(その4):「時は金なり」=おカネは回転して増えていく
儲ける仕組みの核心の一つ「時は金なり」を解説します。
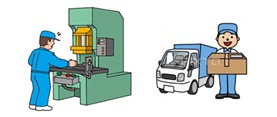
経済を回す両輪が「生産」と「購買」であることは、誰もが分かっています。
 かつ、この両輪を回す原動力が「おカネ」であり、
かつ、この両輪を回す原動力が「おカネ」であり、 「情報」はその潤滑油であることも分かっています。
「情報」はその潤滑油であることも分かっています。この潤滑油が良質であれば、原動力が多少弱くても、「生産」と「購買」の両輪は抵抗なく早く回ります。

その逆に粗悪な潤滑油であれば、原動力の「おカネ」が強力でも、両輪はがたつき、うまく回りません。

また、 良質な潤滑油となる「情報」は「正確」であると同時に「タイムリー」に提供されなければなりません。
まさに「時は金なり」なのです。

現代は、第4の産業革命と言われる「情報革命」の最中(さなか)にあり、その“回る”速さは増すばかりです。

情報が速く回れば当然に経済の回転も速くなり、回転が速くなればなるほど経済の規模は膨れ上がっていきます。
やがて「おカネ」は後回しになり、情報のみで取り引きが進展していくことになります。
かくして、経済を回す原動力のはずの「おカネ」より、潤滑油であるはずの「情報」の持つ力のほうが強くなっていきます。
すでに消費者の多くは「おカネ」の代表である現金ではなく、スマホを介した「情報」で買い物を行っています。
こうした小口の購買の世界では、すでに「おカネ」は消えかかっているのです。
<ちょっと一服>
やがて「おカネ」は後回しになり、情報のみで取り引きが進展していくことになります。
かくして、経済を回す原動力のはずの「おカネ」より、潤滑油であるはずの「情報」の持つ力のほうが強くなっていきます。
すでに消費者の多くは「おカネ」の代表である現金ではなく、スマホを介した「情報」で買い物を行っています。
こうした小口の購買の世界では、すでに「おカネ」は消えかかっているのです。
<ちょっと一服>

ところで、このコラムの作者である私は、コンビニでは消えかかっている「現金」で買い物しています。
理由は「スマホ買いは必要以上に買い込んでしまう」からです。
つまり、現代の高速回転の経済の中に取り込まれないための自衛策です。
「現金」買いだと、「これは我慢しよう!」となるケースが多くなるのは、
みなさんも同じだと思います。
しかし、私のような者は少数派です。
「ネットやスマホ決済での買い物」は、その便利さが一番の魅力ですが、
「こんなにおカネを使って・・」という一種の罪悪感から逃れることができる要素が入り込んでいるのではないかと思います。
私は、不便を感じても、この魔力に逆らっていたいのです。

少し脱線したので、話を本筋に戻します。
上記のコンビニの例で分かるように、「現金」という「おカネ」でなく、「スマホ決済」という「情報」で買うと、経済の回転は速さを増し、回転速度の二乗に比例して“大きく”なります。
こうした原理は物理の法則で証明されています。
「それが分かっていて、また経営者なのに、あんたの現金買いは“おかしい”だろう」と突っ込まれそうですね。
確かにそうです。企業取引の世界は、ほゞ全てが「情報決済」であり、その結果の数字が銀行口座に入り、そして数字が増えたり減ったりするだけです。
もはや「おカネ」は数字情報であり、札束もコインも登場しません。
しかし、コンビニで買い物する時は、企業経営者ではなく一人の個人です。
だから、おカネの出だけは、遅く、そして小さくしていくことを心掛けているのです。

また脱線しましたが、「おカネは回転して増えていく」に戻ります。
おカネ本体より、おカネ情報を「速く、大きく」回すことで「より大きく」増えていくことは、読者のみなさまは実感されていることと思います。
この理屈は個人でも同じなのですが、大金持ちと違い、私個人の経済は小さいので、おカネを大きく使ってしまうと、戻って来る前に破産しそうなので、怖いのですね。
しかし、企業経営が個人と同じになってしまい、「とにかく節約だ。何も買うな」となってしまうと、戻ってくる利益は当然小さくなってしまいます。
もちろん、使い道のない「無駄遣い」を勧めているわけではありません。
やがて、売上そして利益となって戻ってくる使い方が必要です。
ですが、企業は戻りが100%ではない「投資」にも資金を投入する必要があります。

この「投資」は、確実なリターンが見込める投資もあれば、当たればデカイが、返ってこない割合の高い投資もあります。
前者のほうが「危険は少ないが、儲けも低く」、後者がその逆なのは当たり前です。
このどちらを狙うかは経営判断ですが、後者を重視する投資が第1回で説明した「A:一か八か」の一攫千金狙いであり、前者の投資が、「B:儲かる仕組み作り」への投資というわけです。
そのどちらが良いかを論じることは無意味です。
企業の多くは、A・Bミックスの投資を行っています。
このミックス具合とリターンまでのサイクルを考えることが「事業計画」であり、計画実現へのフォローと是正、再実行というサイクルがPDCA(Plan→Do→Check→Action)というわけです。

こんなこと、本コラムをお読みの方には「釈迦に説法」でしょうが、こうしたサイクルを常に整備し必要な改良を継続している企業は、そう多くはないのです。
私自身、本コラムを書いたことで、久しくサイクルのメンテをさぼっていたことを反省しています。

ところで、本コラムの本題である建設ビジネスですが、ビジネスサイクルの回転速度が絶望的に遅い業種です。
完成引渡しまでの長さを考えれば仕方ないのですが、その間のおカネの情報が見えないのは困ります。
そこで、「完成工事未収入金」および「未成工事支出金」という財務科目を考え出したのです。
前者は「完成したのに、まだ入って来ないおカネ」で、後者は「完成していないが、先におカネを払ってしまっている材料費や労務費用」です。
ところが不思議なことに、建設会社の財務諸表には「完成したら、いくらのお金が入るのか」という情報がどこにも無いのです。
それはそうです。
法人税の基となる財務諸表には、確定した情報しか乗せられないからです。
だから、未確定の「○○円が入るはず」という情報が無いのです。
建設中の建物や道路などは「1円の利益」も生まず、完成しない限り、発注した施主は完成物を使って儲けることが出来ず、建設会社や専門工事会社も、必要な代金のすべてを受け取ることができないという構図になっているからです。
その間の「不足するおカネ」を繋ぐのが金融機関の役目ですが、こうした間接金融に頼っていることが建設ビジネスの大きな弱点になっています。
この過程で行き詰る企業が一定の割合で出ることが、この不安定さを象徴しています。

このような借入ではなく「投資」で資金を調達する仕組みが「当たり前になっていない」ことが建設産業の最大の弱点といえるのです。