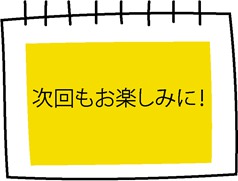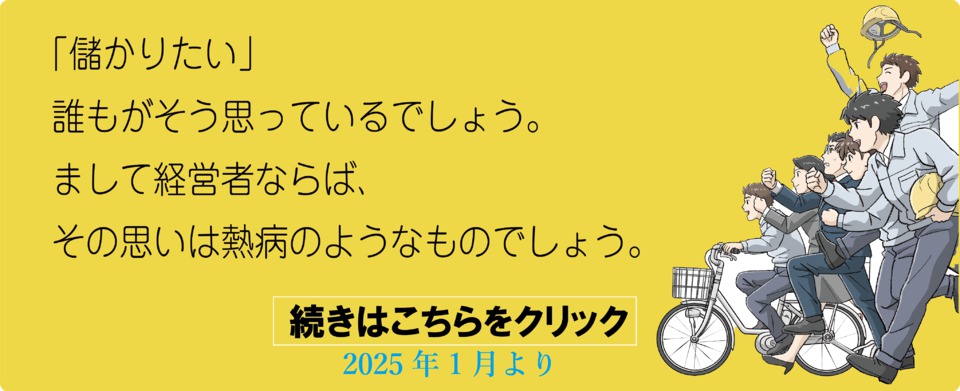「儲かる仕組み」の理解(その7):「儲けさせる」ことが「儲け」となる
2025.06.12
「儲かる仕組み」の理解(その7):「儲けさせる」ことが「儲け」となる
前回(その6)では『固定費の何か月分の資金を確保しておくべきか』という話をしましたが、
この資金確保が、利益を上げる間の「時間稼ぎ」であることはご理解できると思います。
当然、この稼いだ時間の間に次の利益を上げる、あるいは利益を上げるための活動を活発化させる必要があるわけです。
つまり「おカネは時間で考える」ことが、企業経営の生命線というわけです。
そして、PDCA(Plan→Do→Check→Action)サイクルがその具体的手法ということです。

「そんなこと、分かっているよ」と言われそうですが、PDCAサイクルを具体的に実行することの難しさを実感されている方は多いと思います。
計画(Plan)はしたが、実行(Do)できず、実行したが結果の検証(Check)をせず、検証しても改善行動(Action)は“おざなり”は、よく見られる光景で、みなさまも「そう、そう」と思い当たる節が多いのでは・・。
かく言う私も同様で、毎度、反省ばかりしています。

PDCAサイクルは、きちんと回せば確かに効果がある手法です。
しかし、上記で述べたように、途中で頓挫してしまうことが多いのも事実です。
この頓挫を防ぐ手法もありますが、それについては、次のシリーズ(「儲ける仕掛け」の実践)で解説します。ぜひ、この先も本サイトを継続してご覧ください。
ところで、今回の表題「儲けさせる」ことが「儲け」となる ですが、このブログを継続してお読みのみなさまは何となく分かったのではないかと思います。
そうです。
「他人や他社を儲けさせることで自分や自社が儲かる」という仕組み(サイクル)を作ることです。
一直線のレールの上を突っ走るようなビジネスもありますが、追及したいのは、円軌道の上を回りながら少しずつ上に上がっていく「スパイラル(螺旋)軌道」をたどっていくビジネスです。
その軌道を回りながら、少しずつ上に上がっていく動力になるのが「他を儲けさせる」ことという考え方です。
この儲けさせる相手の第一は、もちろんお客様です。
お客様が自社の商品を購入してくださる、あるいはサービスを依頼してくださるのは、それによってお客様自身の儲けに繋がる期待感からです。
「そんなこと分かってるよ」と怒られそうですが、どのレベルまで“分かっている”のかが大事です。

例えば、商店で物販業を営んでいるお客様が、建築会社にお店のリフォームを頼む場合を考えてみましょう。
これは簡単ですね。
リフォームしたことで、来店客が増えた、売上が増えた、新たなお客様が得られた・・などなど、があれば、そのお客様を「儲けさせる」ことが出来たといえます。
ですが、このレベルで止まったのでは、自社の「儲け」としては「一過性」で終わってしまいます。
まあ、「レベル1」としておきましょう。

さらに追加のリフォームや他の依頼を頂ければ、自社の「儲け」がさらに増える可能性があります。
このレベルが「レベル2」でしょうか。
ですが、ほとんどの方は、ここまでです。
では、その上、「レベル3」は、どのような例でしょうか。
それは、このお客様が、他のお客様を紹介してくださることです。
当然、これは自社にとっては大きな利益に繋がります。
(なかなか無いのですが・・)

そのためには、お客様との“意味のある”継続的な接点を持ち続けることが大事です。
しかし、「意味のある接点」、それも「継続する」ことは簡単ではありませんね。
「意味ある」とは、お客様側から見て、その接点が楽しいことが第一です。
「やあ」、「お元気」、「良い天気ですね」という軽い挨拶も楽しさが自然に出るか、それとも無理しているかぐらいは、自己確認できるでしょう。

まずは、そこからチェックしましょう。
その先は、やはり、次のシリーズ(「儲ける仕掛け」の実践)で解説していきます。
さて、その上はあるでしょうか。
あります!
それは、お客様が自社の営業マンになってくださることです。
といっても、お客様が営業マンになって動き回るということではありません。
知り合いなどに、あなたの仕事結果の自慢をしてくださることです。
最近は、Uチューブなどで様々な自慢発信が盛んになっています。
この発信をしてくださるお客様は、まさに新時代の営業マンといえます。
このレベルが「レベル4」といえるのですが、お客様の多くは素人ですから、逆効果となる危険もあります。

最近は、そうしたネットでのトラブルや憎悪の拡散が深刻化するケースが増え、時には大変な事態になるケースも出てきています。
効果が髙ければ、同等にリスクも高いことをしっかりと認識し、事前にトラブル対策も練っておく必要があります。
通販を含めたネットでの商売や営業は、今や様々な商売における営業最前線を席巻してしまった感があります。
もう後戻りはできない状況といえますが、一方で深刻な負の側面も増える一方です。
結果、商売の破綻に繋がるようなケースも出ています。
実は、私の知り合いのスーパーも、そうした事業破綻に追い込まれました。
「レベル4」の仕組みは魅力ですが、危険と隣り合わせの仕組みであることの認識も必要です。
次のシリーズでは、その危険への対処法についても論じたいと思います。
この「儲けさせる」ことが「儲け」となる・・ には続きがあります。
それは、次回の「その8」でお話しします。