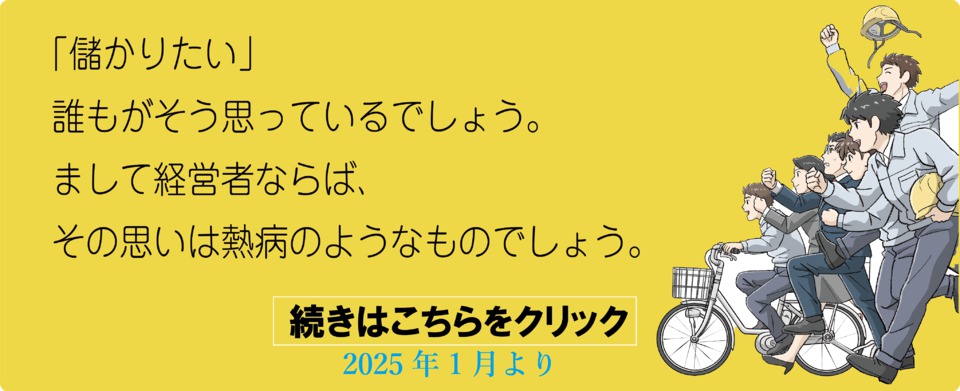「儲かる仕組み」の理解(その3):利益の相反構造
2025.02.16
「儲かる仕組み」の理解(その3):利益の相反構造

(その2)で「等価交換が商売の大原則」と述べましたが、あくまでも“原則”です。
売り手が提示した金額を買い手が“納得”すれば、その取引は等価交換といえます。
かつ、合意金額には売り手の利益が含まれているのが普通ですが、 買い手がその金額を分かっているケースはほぼありません。
つまり、買い手は「見えない」売り手の利益を含めて「納得の価格」と認識したことになります。
このように「売り手の利益」を含めることが“理想”の等価交換です。
ここで少し考えてください。
このような「等価交換」取引は理想ですが、ほんとうに“理想かどうか”は分かりません。
もしかしたら、買い手は「高いな」と思っても「しょうがない」と妥協したのかもしれません。
逆に、売り手は必要な利益どころか、原価割れでも「仕方ない」とした合意かもしれません。

売り手が提示した金額を買い手が“納得”すれば、その取引は等価交換といえます。
かつ、合意金額には売り手の利益が含まれているのが普通ですが、 買い手がその金額を分かっているケースはほぼありません。
つまり、買い手は「見えない」売り手の利益を含めて「納得の価格」と認識したことになります。
このように「売り手の利益」を含めることが“理想”の等価交換です。
ここで少し考えてください。
このような「等価交換」取引は理想ですが、ほんとうに“理想かどうか”は分かりません。
もしかしたら、買い手は「高いな」と思っても「しょうがない」と妥協したのかもしれません。
逆に、売り手は必要な利益どころか、原価割れでも「仕方ない」とした合意かもしれません。

つまり「本当のことはわからない」のです。
また、売り手と買い手、双方の利益は相反するのが普通であり、双方とも、それを理解しています。
また、売り手と買い手、双方の利益は相反するのが普通であり、双方とも、それを理解しています。
ということは、等価交換は“理想に過ぎない”幻想といえます。
売り手側が「どうしても売りたい」となれば、等価から下げた売値となり、その逆であれば、買い手側は等価から高い買値となります。
これが「利益の相反構造」ですが、この相反構造をコントロールすることが儲けに繋がるわけです。
「そんなこと、分かっとるわい!」と怒らないでください。
では、売り手側におられる方にお尋ねします。
自社の商売の“個々の”商品やサービスの「等価交換」となる金額がいくらかを把握されていますか。
また、その金額を算出する計算式は明確になっていますか。
こう問われて即答できる方は、きちんと利益を確保する堅実な商売をされている方でしょう。
反対に、等価構造に注意を払うことなく商売を行っている会社は、損をしているのか儲けているのかが分からず、たとえ儲けていても顧客の不満から信頼を失っていることにも鈍感になってしまいます。
身に覚え、ありませんか?
まあ、あっても無くても続きを読んでください。

誰でも自分の儲けは増やしたいものです。
ゆえに、等価交換より「自分に利がある取引」を狙います。
「そんなの当たり前だろ。早く儲ける話をしろ」と怒られそうですが、待ってください。
利益の相反構造を自分に有利なようにコントロールするのは、そう簡単な話ではありません。
取引先の相手がいるからです。
「こっちが買い手の場合なら有利だろ」と言いたいでしょうが、それは短絡発想です。
最近は「不当な買いたたき」が問題視され、公取委の立ち入りさえ受けることがあります。
こうした法的な問題はさておき、商取引は「等価交換」が原則であることを改めて考えてください。
かつ、出来るだけ大きな利益が欲しいという矛盾する気持ちが生ずるのは商売の当たり前です。
つまり、商売の儲けは「等価交換」と「利益の相反」のバランスの中にあります。
では、このバランスの取り方に何らかの法則はあるのでしょうか。
それを考えてみましょう。

物販業なら、売り手は買い手に対して「お買い得ですよ」と言って、購買意欲を刺激します。
この言葉を聞いた時、買い手の心理はどう反応するでしょうか。
おそらく『いつものトークだ』、『そうは思わないな~』と思うか、あるいは『ウソだろう』、『騙されないぞ』ではないでしょうか。
では、住宅のセールスマンが、原価5000万円の家を5000万円で売る場合を考えてみましょう。「原価=売価なので、利益の相反構造がなく、理想の取引だ」となるでしょうか。
利益ゼロの商売ですから、なるわけはありませんね。
上司から「ばかやろう」と言われるのがオチです。

それでは、10%の利益を乗せて5500万円にしたらどうでしょうか。
買い手側には、この利益構造は分かりません。
お客の多くは「高いね、もっと安くならないの」と言うでしょうね。
心の中では「思ったより安いな」と思っても「OK」とは言わず、値切ろうとする顧客のほうが多いことが普通です。
しかし、お客は原価が分からないまま値切ってきます。
というより、そもそも原価に対する関心はなく、ただ「提示価格で買うのは損だ」との思い込みで値切ってくるのです。
こうして「利益の相反構造」が顕在化してしまうと、後は双方の駆け引きになってしまいます。
ゆえに、売り手は「利益の相反構造」を頭に入れておく必要がありますが、この構造を顕在化させてはいけないのです。
買い手に「妥当な価格だな」と思わせる工夫と努力が必要です。

と、ここまでの解説で理解されたと思いますが、売り手、買い手の双方が「等価交換だ」として合意形成することは、たいていの場合、無理です。
しかし「利益の相反構造」のことは、明確ではないが双方とも理解はしているのです。
ゆえに売り手は、相反構造を不明確なままにして、自社の適正利益を確保しつつ、買い手が納得すると思われる金額を提示するわけです。
しかし、だからといって、利益の相反構造に無頓着で良いというわけではありません。
根拠がしっかりとした計算式を確立し、その計算式をメンテナンスしながら、顧客への提示価格をコントロールすべきなのです。
次回は、儲ける仕組みの核心の一つ「時は金なり」を解説します。
買い手側には、この利益構造は分かりません。
お客の多くは「高いね、もっと安くならないの」と言うでしょうね。
心の中では「思ったより安いな」と思っても「OK」とは言わず、値切ろうとする顧客のほうが多いことが普通です。
しかし、お客は原価が分からないまま値切ってきます。
というより、そもそも原価に対する関心はなく、ただ「提示価格で買うのは損だ」との思い込みで値切ってくるのです。
こうして「利益の相反構造」が顕在化してしまうと、後は双方の駆け引きになってしまいます。
ゆえに、売り手は「利益の相反構造」を頭に入れておく必要がありますが、この構造を顕在化させてはいけないのです。
買い手に「妥当な価格だな」と思わせる工夫と努力が必要です。

と、ここまでの解説で理解されたと思いますが、売り手、買い手の双方が「等価交換だ」として合意形成することは、たいていの場合、無理です。
しかし「利益の相反構造」のことは、明確ではないが双方とも理解はしているのです。
ゆえに売り手は、相反構造を不明確なままにして、自社の適正利益を確保しつつ、買い手が納得すると思われる金額を提示するわけです。
しかし、だからといって、利益の相反構造に無頓着で良いというわけではありません。
根拠がしっかりとした計算式を確立し、その計算式をメンテナンスしながら、顧客への提示価格をコントロールすべきなのです。
次回は、儲ける仕組みの核心の一つ「時は金なり」を解説します。