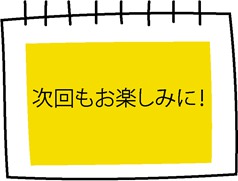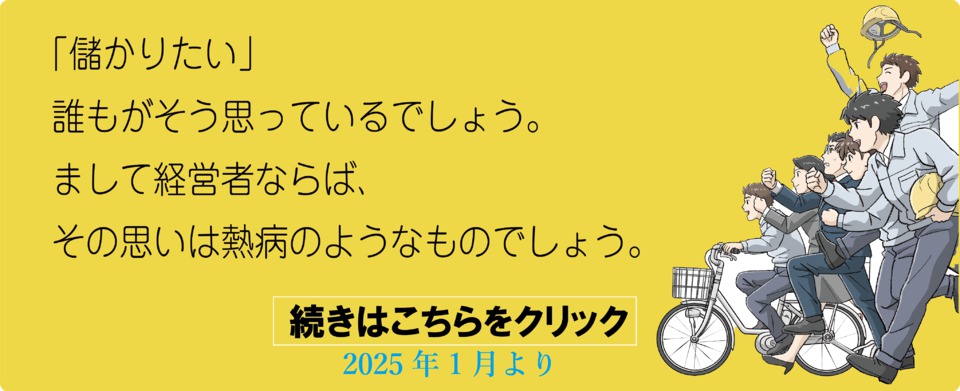「儲かる仕組み」の理解(その5):賃上げと値上げの好循環
2025.04.03
「儲かる仕組み」の理解(その5):賃上げと値上げの好循環
日本は30年に及ぶ長期デフレで、国民の意識がデフレ・マインドに張り付いてしまいました。
なにしろ10歳の子供だった人は、40歳までデフレ経済の中で成長し、社会人としての前半期を過ごしたわけです。
意識がデフレに張り付いてしまうのも無理はありません。
ここ数年、ようやく給料が上がってきましたが、それ以上に物価が上がったことで、国民の意識はデフレ・マインドから抜けることができていません。
デフレの象徴ともいえる「100円ショップ」がまだ健在なことも、その象徴といえます。
(100円ショップが悪いわけではありませんが・・)

そうした停滞ムードの中、政府は「働き方改革」と称する、企業の従業員が働く時間を強制的に制限する政策を打ち出しました。
その結果、残業代が減ったり、時間給の労働者の収入が減るという不満が出ると、その影響を分析することなく、なりふり構わず「賃金を上げろ」と企業に要請(脅し?)を掛けました。
でも、この要請とは無関係に、そもそも人出不足で給料は上がっています。
特に建設産業は、慢性的な労働力不足により、従業員の給料とともに、労務単価の上がり幅が大きく経営の圧迫要素となっています。

なにしろ10歳の子供だった人は、40歳までデフレ経済の中で成長し、社会人としての前半期を過ごしたわけです。
意識がデフレに張り付いてしまうのも無理はありません。
ここ数年、ようやく給料が上がってきましたが、それ以上に物価が上がったことで、国民の意識はデフレ・マインドから抜けることができていません。
デフレの象徴ともいえる「100円ショップ」がまだ健在なことも、その象徴といえます。
(100円ショップが悪いわけではありませんが・・)

そうした停滞ムードの中、政府は「働き方改革」と称する、企業の従業員が働く時間を強制的に制限する政策を打ち出しました。
その結果、残業代が減ったり、時間給の労働者の収入が減るという不満が出ると、その影響を分析することなく、なりふり構わず「賃金を上げろ」と企業に要請(脅し?)を掛けました。
でも、この要請とは無関係に、そもそも人出不足で給料は上がっています。
特に建設産業は、慢性的な労働力不足により、従業員の給料とともに、労務単価の上がり幅が大きく経営の圧迫要素となっています。

その中で、30万円を超える初任給を打ち出す企業も現れ、初任給バブルの様相すら見せています。
あのバブル時代、私は管理職でしたが、高騰する初任給とは裏腹に新入社員の質は下がる一方で、ついに人事部に対し「うちの部署にはもう新入社員を配属するな」と申し入れました。
所属していた会社は、初任給だけでなく、新入社員一人ひとりにワンルームマンションまで与えるなど、異常状態になっていきました。
先輩社員たちが三畳一間の社員寮に入れられているのに・・と、腹が立ちました。
そうした先にバブルが破裂したわけです。
「あの時の二の舞になってきたな」と、この先が不安です。
話を戻します。
円安の進行で原材料の仕入れ価格が上昇し、人件費上昇とのダブルパンチに堪えられなくなった各企業は、一斉に製品やサービスの値上げを始めています。
こうした状況を見て、政府は御題目のよう唱えている「賃上げと値上げの好循環」が回り出したと言うつもりなのでしょうか。
ここで私の昔話をお聞きください。
かっての日本は、政府が「賃上げしろ」などと脅さなくても、自主的な賃上げが続いていました。
もう大昔になりますが、私が社会人となった時の初任給は3万円/月でした。
それから21年後のサラリーマン最後の月給は80万円でした。
実に26.6倍になったわけです。
当然、物価も上昇しましたが、一杯50円のラーメンが800円ぐらいになっていますから16倍です。

ちなみに、私の親が5万円/坪で買った土地を18年後に売却した時は80万円/坪と、これも16倍になりました。
このように物価は16倍ぐらい上昇しましたが、賃金はその物価の1.66倍のペースで上がったため、おう盛な購買意欲が起き、日本経済全体を押し上げたわけです。
この間、政府が企業に「賃上げしろ」なんて言ったことは一度もありませんでした。
つまり、当時は「賃上げと物価上昇の好循環」が自然に起きていたわけです。

しかし今は・・政府と「大企業労組中心」の連合が手を組み、躍起となって賃上げを強制しているようにしか思えないのです。
言い過ぎかもしれませんが、そのように感じるのです。
では、その大企業は、下請けの中小企業も同程度の賃上げができるような価格で発注を行っているでしょうか。
経済誌によると、自社の賃上げに見合う価格転嫁ができている中小企業の割合は、45%ということです。
賃上げ原資の確保に苦労している中小企業が多いということです。
では、こうした状況下で中小企業、とりわけ建設会社はどうすれば良いのでしょうか。
前回の(その4)で述べたように、まずは「時は金なり」の意識を強く持ってください。
さらに「おカネは回転して増えていく」の意識も大事です。

建設業は契約成立までの時間が長く、この間、おカネは入らないのに費用が出ていく営業スタイルになっています。
時折「見積もりは無料です」とアピールする広告を見かけますが、ユーザーからは「そんなの当たり前だろう」と思われるだけの無駄アピールです。
しかも、受注しても、完成までの時間が長く「ビジネスの回転速度が遅い」という、もう一つの弱点を抱えています。
残念なことに、建設会社で働く人は、こうしたことに対する理解が薄いように感じます。
ある程度理解している人も、「仕方ないよ」と思っているだけでしょう。
まずは、こうした「しょうがない病」から抜け出しましょう。
それは難しいことではありません。
まず、自社の企業活動の全てを「カネと時間で考えていく」“クセ”を付けてください。
例えば「今回の広告に掛ける費用は“○○円”で、いくらくらいの時間を掛けて“いくら”の受注を狙うのか」を考えて計画し、そして結果のフォローを行うというように、です。
このように物価は16倍ぐらい上昇しましたが、賃金はその物価の1.66倍のペースで上がったため、おう盛な購買意欲が起き、日本経済全体を押し上げたわけです。
この間、政府が企業に「賃上げしろ」なんて言ったことは一度もありませんでした。
つまり、当時は「賃上げと物価上昇の好循環」が自然に起きていたわけです。

しかし今は・・政府と「大企業労組中心」の連合が手を組み、躍起となって賃上げを強制しているようにしか思えないのです。
言い過ぎかもしれませんが、そのように感じるのです。
では、その大企業は、下請けの中小企業も同程度の賃上げができるような価格で発注を行っているでしょうか。
経済誌によると、自社の賃上げに見合う価格転嫁ができている中小企業の割合は、45%ということです。
賃上げ原資の確保に苦労している中小企業が多いということです。
では、こうした状況下で中小企業、とりわけ建設会社はどうすれば良いのでしょうか。
前回の(その4)で述べたように、まずは「時は金なり」の意識を強く持ってください。
さらに「おカネは回転して増えていく」の意識も大事です。

建設業は契約成立までの時間が長く、この間、おカネは入らないのに費用が出ていく営業スタイルになっています。
時折「見積もりは無料です」とアピールする広告を見かけますが、ユーザーからは「そんなの当たり前だろう」と思われるだけの無駄アピールです。
しかも、受注しても、完成までの時間が長く「ビジネスの回転速度が遅い」という、もう一つの弱点を抱えています。
残念なことに、建設会社で働く人は、こうしたことに対する理解が薄いように感じます。
ある程度理解している人も、「仕方ないよ」と思っているだけでしょう。
まずは、こうした「しょうがない病」から抜け出しましょう。
それは難しいことではありません。
まず、自社の企業活動の全てを「カネと時間で考えていく」“クセ”を付けてください。
例えば「今回の広告に掛ける費用は“○○円”で、いくらくらいの時間を掛けて“いくら”の受注を狙うのか」を考えて計画し、そして結果のフォローを行うというように、です。

経営者は、経営全体をこのようなサイクルの中で計画し、その中に賃上げや賞与の計画も組み込み、その効果の検証を実行していく。
こうした計画・実行のサイクルを自社の中に定着させることが出来れば、企業力は間違えなく上がっていきます。
「そんなこと分かっているよ」と言われますか?
あるいは、「でも面倒だし、計画したって、その通りにはいかないから無駄だよ」と言われますか。
そうならば、だから“やるべき”なのです。
売上額そして利益額を計画的に確保していかないと、計画的な賃上げもできず、社員の離反を招き、新たな人材の確保ができないのは当然ではないでしょうか。
もちろん計画したからといっておカネが計画的に出入りすることはなく、常に狂います。
だから、そうした計画の狂いに備えて一定額の資金確保をしておくことが大事なのです。
その話は次回に。